概念とは
ものごとを捉えたり、新しいものを生み出したりする際に重要となる思考能力である概念思考について考えましょう。
実は、本サイトのコンテンツは、概念思考を指向するように努めて記載しています。ですので、コンテンツと併せてこの「概念思考」を意識していただきたいと思います。
「概念」とは何か? 辞書で引いてもなかなかピンとくる記述はなかったりします。「包括的」という記述が多いですが漠然としています。では、明確にします。概念とは「分類」です。
具体的に考察するため、えんぴつとシャーペンで考えてみましょう。
この二つ、大きなくくり(分類)では、同じ「筆記具」です。これを上位概念といいます。しかし、名称が違うのですから、別物であり、これらを区別する分類の仕方があります。この、「二つを区別する分類の仕方」が「下位概念」になるのですが、単純に「違う」ではだめで、この違いを「明確に」、「適切に」「言葉で表現」して初めて「下位概念」となります。つまり、えんぴつを、シャーペンとの違いにおいてえんぴつ成らしめているのは何かを明確化することです。この分類する能力が概念思考力となります。
では、この分類を実際に考えてみます。まずこんなのはどうでしょう。
「えんぴつは木でできていて、シャーペンは鉄が使われている」(分類表現A)
確かに、ある意味、違いを言葉で説明していますが、「適切」な概念としては不十分です。恐らく、小学生の大多数はこのような回答をすると思います。概念思考が未熟である故の回答ですが、小学生であれば十分です。むしろ、良く観察していると褒めるべきところでしょう。
正しく分類するには、世の中にあるえんぴつやシャーペン、さらには今後現れるものも含めて完全に包含する表現でなければなりません。木ではないえんぴつや鉄が使われていないシャーペンもありえますし、これからも登場するかもしれません。
では、これはどうでしょう。
「えんぴつは削って芯を出し、シャーペンは書く方と反対側のボタンを押すことで芯を出す」(分類表現B)
なかなか良い感じです。でも、これは分類が細かくなりすぎています。本体が紙でできていて「剥く」ことで芯を出すえんぴつがありますし、振って芯を出すシャーペンがあります。
最も適切な概念的表現は以下のようになると思います。
「えんぴつとは、「芯」を「材」で取り巻き、「芯」の使用による減りに合わせて「材」を部分的に除去することで「芯」を露出させて使用する筆記具であり、シャーペンとは、「芯」を送り出す機構を持つ筆記具である。」(分類表現C)
要するに、「えんぴつは本体を縮ませることで芯を出し、シャーペンは送り出すことで芯を出すもの」ということです。
これが「本当」のえんぴつとシャーペンの「違い」であり、分類のポイントなのです。この「本当の違い」を認識できる能力(違いに辿りつける能力)が概念的に捉える能力ということになります。上記の三つの表現を図示すると以下のようになります。えんぴつの表現のみ示しています。
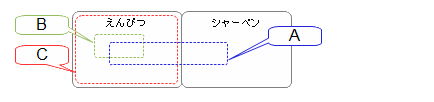
Aは「木でできている」ですが、木でできているシャーペンもありますので、こうなります。Bは「削って芯を出す」ですので、シャーペンに入ることはないですが、「剥いて芯を出す」鉛筆があるので、こうなります。Cはえんぴつの定義そのものなので、完全に一致するわけです。
今度は、逆に、えんぴつとシャーペンを同一の概念で捉えてみましょう。先に「筆記具」という上位概念を出しましたが、「筆記具」の中には、ボールペンや万年筆、筆などがあります。これらとの違いを考え、「筆記具」の一ランク下の上位概念でまとましょう。
まあ、最初に思い浮かぶのは、「消せる」ということだと思います。良いのですが、厳密に言うと、「消せる」のはえんぴつやシャーペンで書かれた文字等のことで、えんぴつやシャーペン自体のことを表現したものではないのです。従って、「なぜ消せるのか」を考えて、えんぴつやシャーペン自体の概念として抽出する必要があります。上記のえんぴつとシャーペンの概念で、「芯」という共通の要素が出てきました。この芯を明確化するわけです。この芯は、「書く相手(紙)に対し、書いた際の摩擦により芯を粉末化させて付着させ、記述内容として残すもの」となります。これが、えんぴつとシャーペンに共通し、他の筆記具と分類させる概念になります。消しゴムで消せるのは、消しゴムは、この付着した粉末を取り除けるためです。他の筆記具でインクを使うものは、紙にインクを染み込ませることで残しますので、消しゴムでは消せません。この点が他との違いになります。(※ 上記で「書く相手」としているのも概念的表現です。書く対象は一般的には「紙」ですが、木材やプラスチックもあります)
ここで、この「消せる」というポイントについて、もう少しだけ考えてみましょう。上記では、最初に、えんぴつ、シャーペンの共通概念として「消せる」ことを挙げ、考察をスタートしましたが、色えんぴつは、消せるという分類には入れにくいです。なぜえんぴつは消せて、色えんぴつは消せないのでしょうか。これは、芯を粉末化した際の粒度(粉末の細かさ)の違いのためです。粒度が荒いと、紙の表面に付着する程度ですが、細かいと紙の繊維の間にまで入り込み、除去(消す)することが困難になるのです。この粒度の違いが、消せるか消せないかにつながります。すなわち、粒度が非常に細かくなると「液体」になり、筆記具の観点では「インク」となるわけです。
概念思考は、本質の追及でもあります。えんぴつとシャーペンの違いを概念的に捉えるには、本質の追及が必要です。
例えば、えんぴつが木でできているということは、シャーペンとの違いを捉える上では、枝葉でしかなく、本質ではないわけです。本質の追及には、「なぜ」を考えることです。すなわち、そうである理由です。木であることの理由としては、以下があげられると思います。
- 作りやすい
- 削りやすい
- 持った感じに温かみがある
- 木の香りがする
- 噛みやすい
えんぴつの本質に結びついているのは「削りやすい」ぐらいでしょう。列挙した理由に基づき、シャーペンにも適用できる(シャーペンのホルダを木で作る)のであれば、それはえんぴつの本質ではありません。最後の「噛みやすい」はまあ、おまけですが、小学生の頃の私の筆箱の中のえんぴつはほとんど歯型がついてました・・・。小学生の私にとっては、「噛める」のはえんぴつの魅力だったかもしれません。
お店や組織のコンセプト
概念は英語ではConcept(コンセプト)です。この言葉の方が身近かもしれません。この言葉はサービス業のお店などでも使用されます。「当店のコンセプトは~です」といった形です。これも分類です。より適切に言えば、「差別化」ということになります。他店と差別化し優位点を端的な言葉で表現しているわけです。「当店のコンセプト」として明確化することは、お客へのアピールに加え、店のスタッフの意識を上位概念で統一させる意味もあります。聡明なスタッフであれば、上位概念が示されたことで、その意味を理解し、下位概念としての行動規範に結びつけます。
私が大学生のころ、東京の西麻布にあったビリヤード場でバイトをしていました。このお店、ビリヤードと言っても、英国で中心的に行われているSnookerという種類のものなのですが、場所柄と共に、店の雰囲気等も一般的なビリヤード場とは一線を画すものでした。まあ、私は単純にSnookerが好きなのでバイトに入れてもらっただけで、雰囲気的には、むしろ場末的なピリヤード場の方が性にあっていたのですが。
そのバイトで最初に渡されたのが、数ページのマニュアルです。このトップに書かれていたのが、「コンセプト:大人の社交場」でした。このコンセプトに基づいて行動しろということです。私も含め二十歳そこそこのスタッフでは、この「大人の社交場」に沿った行動規範はなかなか難しいのですが、そのマニュアルには、例が記載してありました。今でも印象に残っているのは、お客様に「昨日はありがとうございました」というのはご法度(禁止)という記述です。そのお客様は連れの方に嘘をついて昨日、ご来店されている可能性があるためです。つまり、この例は「お客様のプライベートには絶対に踏み込まない」という下位概念を行動の具体例として示したものであり、もちろん、それは「大人の社交場」という上位のコンセプトを堅持するために生まれる下位のコンセプトであるわけです。
別のお店で、「当店のコンセプトは家族です」という居酒屋があると、スタッフの対応は全然別物になるでしょう。プライベートにも踏み込みまくりで、「お袋か!」と言いたくなる女将がいて、それが好きで訪れる人で成り立つことになるでしょう。
えんぴつの話から、随分とずれた印象があるかもしれませんが同じです。このような概念思考はあらゆる場面で有効です。
本質とレベル
概念思考では本質を追及することになりますが、本質を突き詰め過ぎると、行き過ぎて哲学の範疇にまで入り込んでしまいます。
企業での商品開発で、「ユーザにとって良いもの」を追及するとします。「ユーザがハッピーになれるもの」→「ハッピーとは」→「便利だったり、快適だったり」 このあたりまではいいでしょう。ところがこのあたりから「そもそも便利がハッピーになるのか?ある面の便利さが逆に人間らしさを阻害しないか?」→「人間らしさとは」→「人間らしさの追及が自然を破壊し、人類の危機につながらないか」・・・という具合で訳が分からなくなります。「本質を追及しろ!」という大号令を受けて検討すると、こんなことになりかねません。そこで理解してもらいたいのは、「本質にはレベルがある」ということです。「本質」なんて言うと、何やら「単一の真理」のようですが、ケースバイケースで、その深さを変えるということです。先に、「えんぴつ」の例で示しましたように、「シャーペン」と区別する場合と、「シャーペン」を同類とする場合で、捉えるべき概念が違いました。ここに本質のレベルがあるわけです。つまり、ある時には、「えんぴつの本質は「削る」ということだ」となり、また、ある時には、「えんぴつの本質は「芯」を使っているということだ」となります。その時々のテーマに応じて最適な「本質」に基づいて検討することになります。
まあ、簡単に言えば、あ、この先まで行くとやばいなと思ったら止めることです。「本質を追及しよう。ただし、レベルは適切に」ということを理解しておいて欲しいです。
例え話
あるものを説明するのに何か別のものに例えることがあります。この例え話は概念思考に基づいて行うべきものです。
本サイトのコンテンツのようなIT技術などは目に見えないものなので、そのまま説明しても理解しにくい場合があります。そこで、別のものに例えるわけですが、この「別のもの」は、説明したい技術と同一の概念でなければなりません。さらに、「別のもの」は良く知られているものでなければなりません。つまり例え話とは、概念を写像し、既に良く知られているもので概念を理解させることでなのです。ここで必要なのは、説明したいものの概念を抽出する能力と、説明したいものと同一の概念を持つものを見出す能力で、何れも概念思考力です。概念思考なしに、「あ、ちょっと似てる」程度で例えると、意味が無いばかりか、誤解を生むこともあります。適切な例えは、例えるだけで、説明していないことも類推してもらえる効果も期待できるのです。
「例え話」の例を挙げてみます。
コンピュータネットワークを構成する技術の理解を指向するには、コンピュータネットワークを「郵便」に例えるのが適切です。「コンピュータからコンピュータに送られるデータは、郵便の封書のイメージで送られます。」これを聞いただけで、「じゃあ、封筒があるの?」「はい。コンピュータ通信では、ヘッダと呼ばれます」、「じゃあ、郵便みたいに、データには相手の住所が付けられるのね?」「はい、封筒に該当するヘッダにアドレスと呼ばれるものが付けられます」「じゃあ、郵便みたいに「速達」とかもあるの?」「はい、あります。同様にヘッダに明記します」「コンピュータネットワークって一回に送れる量って決まっているの?」「はい、封書に定型規定があるように、最大サイズが決まってます。これを超える場合は、複数の封書に分けて送ります」・・・という具合で技術が類推できるわけです。
どうですか? 理解が一気に進みませんか? これは「郵便」の例えが適切であるためです。これが「飛脚」とかになると、「飛脚とか見たことないし・・」「どうやって送っているか知らないし・・」とかになって適切ではなくなります。
私はコンピュータネットワークを「電話」に例えることもあります。先の「郵便」の例えですが、その前段で「コンピュータネットワークを構成する技術の理解」を目的としてる点に注意してください。つまり、コンピュータネットワークを単なる情報の伝達手段として、その中身の送信方法についての理解が不要である人に対しては、「電話」の例えが適切な場合もあるのです。その人に理解して欲しい概念は何か という点が重要であり、それに応じて「例え」も変わるわけです。
新しい技術を説明するのに例え話は有効ですが、「新しい技術」なのに概念で一致するものなんてあるの? という疑問が出てきそうです。その疑問はもっともですが、全く新しい概念などそうそう出てくるものではないのです。IT技術のほとんど全て、人がやってきたことを機械にやらせただけです。逆に云えば、ほとんどの新しい技術は、所詮、身近な現象の概念を写像したにすぎないのです。でも、この誕生に携わった偉人は間違いなく概念思考力で技術を生み出してくれたのです。
ただ、アインシュタインの相対性理論、さっぱりわからない・・・ 多分、全く新しい概念なんだと思います。
概念思考のトレーニング
私自身の概念思考が特に鍛えられたのは、特許の業務に携わっていた頃だと思います。特許の取得には、「請求の範囲」として、特許権を主張する技術を文章で表現して申請し、特許として認められると、この「請求の範囲」に記載された範囲での独占権が与えられます。この「請求の範囲」を適切に表現するためには概念思考が必須なのです。
具体的に説明しましょう。人類で初めて「コップ」を発明したとします。まあ、最初ですから、木をくりぬいて作ったとします。これを独占して、生産、販売するために、特許を取るわけです。さて、請求の範囲をどうしましょう? 最も端的には以下のようになります。
「木で構成され、円筒状で中に空間があり、円筒の一端は解放しており、他端はふさがっており、円筒の横に持ち手がついているもの」
もし、これで権利化されると、「木」が構成要素なので、誰かが陶器で同じものを作ると、別物ということになり、権利が及ばずに自由に生産、販売されてしまいます。また、「木」で升のように四角形で作られると「円筒」ではないので、これも権利が及びません。もちろん、「持ち手」など、完全に余計な限定です。折角、世紀の大発明をしたのに、簡単にマネされて権利の及ばないところで流通してしまうわけです。
では、適切な請求の範囲を示します。
「本体を安定支持する支持部と、この支持部の他方に、支持部に向かって窪みが形成されているもの」
どうでしょうか? これで権利を取ると全てのコップが含まれます。もっといえば、「皿」や、ただの箱も含まれます。極めて強力な権利となるわけです。
※ ちなみに、皿や箱が既に存在していると、この表現で権利は取れません。特許は新しいものでなければ権利化できません。この皿等が存在している場合は、コップとしの利用など自明(ただ深くしただけ)であるとして特許として成立しないのです。既存のものを含まず、最大限大きな概念(上位概念)で捉えて文章化するのが特許出願の必要なスキルです。
※ ちなみに2、この「支持部」の説明が弱いですが、特許出願には、「請求の範囲」の他に、「発明の詳細な説明」を書いて提出します。この説明の中で、支持部として、平らな底、円筒状の底、三脚的なものといろいろな具体例を示すことで、「安定支持」の意味が明確になり、このような記載でも認められます。
いかがでしょうか? コップの概念がこのような表現になるとは思わなかったのではないでしょうか。是非、身近ないろいろなものでこのような概念を抽出するトレーニングをしてみてください。概念思考が身に付くと思います。あ、もちろん、前に説明したえんぴつとシャーペンを比較するようなトレーニングも意味があります。両者ともに同じ思考力が鍛えられます。
いろいろな観点で概念思考について書いてまいりましたがご理解いただけましたでしょうか。
ご理解いただけた方に、ここで注意事項です。概念思考は、論理の塊です。つまり、理屈っぽくなります。自分の頭の中では、物事の理解や整理、新しいものの創造に有効に利用すべきですが、人に対して用いる(説明や議論で)場合には、相手に合わせてください。相手も概念思考になれていると、これほどスムーズなものはありません。理解も早くなりますし、議論は有効な方向に進みます。しかし、相手が概念的思考ができないと、概念的に表現したものが理解してもらえません。先にえんぴつの話の中で、「書く相手」という表現をしましたが、これは概念思考故の表現になります。つまり、概念思考に慣れていると、紙、木材、プラスチック等が頭に浮かび、それを包含する形で表現してしまうのです。概念思考ができない人向けには、ほとんどの場合の対象である「紙」という表現で良いでしょう。ちょっとだけ含ませるなら「紙とかに」という表現も良いかもしれません。